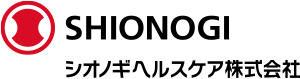特集03-8月
この夏は暑さに負けず体調キープ
夏バテ知らずの元気生活
一日中からだがだるい。
何もする気がおきない。
疲れやすく食欲がない。
そんないわゆる「夏バテ」症状を、今年の夏こそ、しっかり防ぎたいもの。
そこで、夏を元気に乗りきるためのアドバイス情報をご紹介。
暑さなんかに負けず、心身をグッドなコンディションに保ちましょう。
夏バテの原因と基本対策
さらに現代人の夏バテ症状を加速させる要因がエアコンです。人のからだは暑くなったら体温を下げるために汗をかき、寒いときは血管を収縮させて体温の逃げを防ごうとします。ところが効き過ぎるエアコンによる冷えや、室外との過剰な温度差によって、自律神経のバランスが崩れ、こうした調整機能が鈍くなってしまいます。その結果、血行が悪くなって、冷房の効いた室内ではますます冷えを感じるということに。 ひいては全身の倦怠感、頭痛、夏風邪といった体調不良にもつながります。
したがって夏バテを防ぐ基本対策としては、まずエアコンによる冷えをしっかりガードすること。積極的に汗をかいて血行を良くし自律神経のバランスを整えること。そしてぐっすり眠って心身の疲労をためないことです。心持ち速足で歩いたり、休日にはスポーツを楽しんだり、1日に1回は汗をかく習慣を。また夏こそシャワーですませず、40℃前後のぬるめのお湯に20分ほどつかり、からだを温めましょう。就寝前の入浴は快眠効果もあり一石二鳥です。上がる直前に手足に冷水をかければ、手足のむくみを解消するとともに、血行を促します。また寝苦しいときは、冷蔵庫で冷やして使う枕や使いきりタイプの冷却シートなども活用し、快眠を得る工夫をしましょう。

夏こそビタミン補給をしっかりと
とりわけ不足してしまうのが、ビタミンやミネラルです。水分の摂り過ぎで大量に汗をかいたり尿を排泄すると、ビタミンB群やCなどの水溶性のビタミンとミネラルが体外へ出ていってしまいます。 さらに夏は清涼飲料水やアイスクリームなどの甘いものをつい摂り過ぎ、またそうめんなど、さっぱりとした食事ですますことも多いもの。これらの食品の主成分は糖質で、糖質をエネルギーに変えるには大量のビタミンB1が消費されます。このように夏は最もビタミン不足になりやすい季節だといっていいでしょう。全身がだるい、やる気がおこらない、疲れやすい…といった夏バテの典型的な症状も、ビタミン不足に負う部分が少なくありません。

夏太り、夏ヤセはこうして防ぐ
スタミナアップのために、暑い夏こそしっかり食べなきゃ…と思い込んではいませんか。それは大きな誤解で、外気温の高い夏場の基礎代謝量(体温を保つために必要なエネルギー量)は冬場の90%。つまり冬と同じカロリー摂取だと、10%ぶん余分なエネルギーをため込むことに。じつは夏は太りやすい季節なのです。 実際、夏になると体重が増えがちな方も少なくないはず。夏太りは、“スタミナアップ信仰”による食べ過ぎ、糖質の多い清涼飲料水やデザートの摂り過ぎ、運動不足などによって生じます。「夏は太りやすい」ということを頭に入れ、カロリーや甘いものを控える食生活を。
また暑いからといってエアコンの効いた室内にこもっていては、わずかなエネルギー量しか消費されません。ひと駅余分に歩いたり、エレベータをやめて階段を使ったり、おっくうがらず毎日30分以上はからだを動かすようにしましょう。 一方、夏場になると体重が減る、いわゆる夏ヤセは、胃腸の機能低下が原因。暑さで食欲が衰え、冷たいものや水分ばかり摂り過ぎるために、さらに胃腸の消化吸収力が弱まってしまう。これが夏ヤセの典型的なパターンです。たとえ少なめの量でも三食きちんと食べるようにし、スパイスを使った料理や食前酒を楽しむなど、胃腸を刺激して食欲を高める工夫を取り入れましょう。また胃腸のコンディションを高める特効ツボをご紹介。お風呂上がりなどにツボを押し、夏ヤセの解消につとめましょう。
夏ヤセを防ぐ特効ツボ
胃腸の機能を高めて食欲増進[足三里(あしさんり)]
ひざの骨のやや下、2cmほど外側にあるツボ。胃液の分泌を促し食欲を高めるツボです。血行を良くして冷えを解消する効果もあるので、夏ヤセ・夏バテ防止にうってつけ。
![胃腸の機能を高めて食欲増進 [足三里(あしさんり]](/content/dam/shc/jp/special/0308/images/0308-img-03.jpg)
消化器系の疲れを回復[合谷(ごうこく)]
手の甲の親指と人さし指が交わる部分のやや内側のツボ。胃腸など消化器系のはたらきを高めます。人さし指のほうに向かって力を入れて押します。
![消化器系の疲れを回復 [合谷(ごうこく)]](/content/dam/shc/jp/special/0308/images/0308-img-04.jpg)