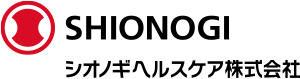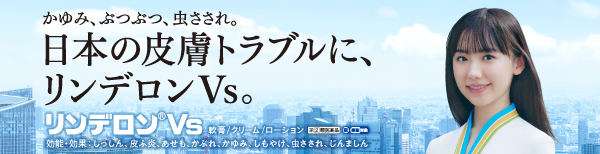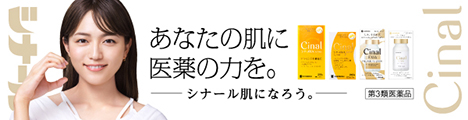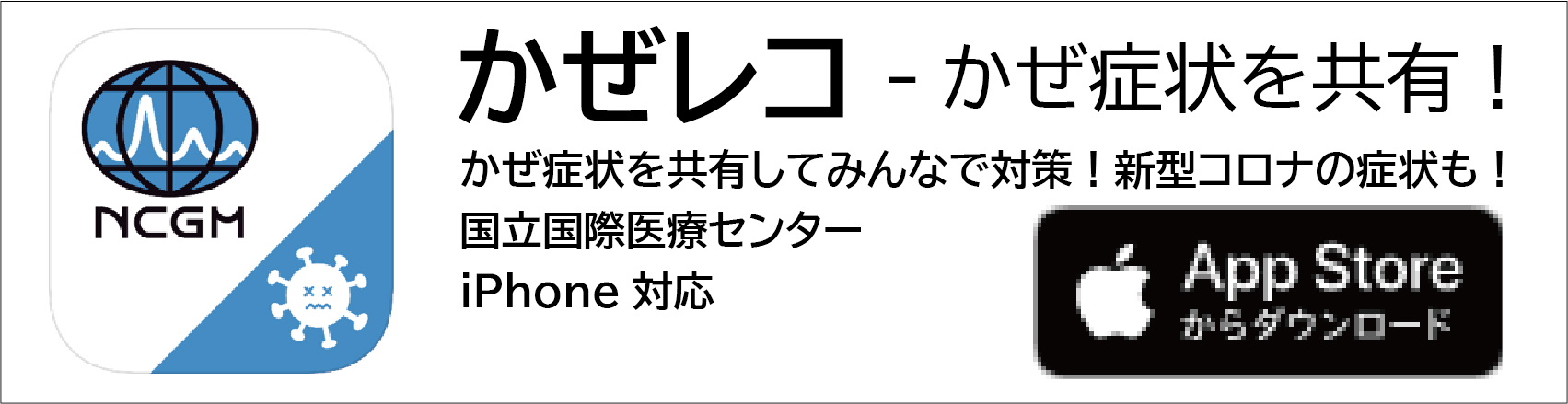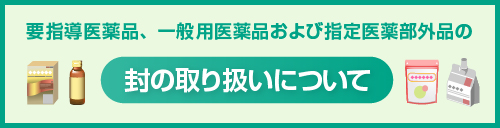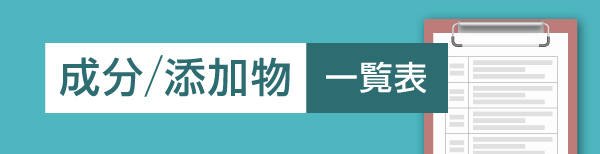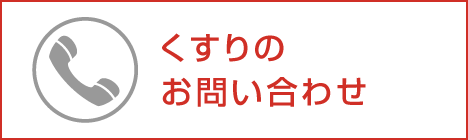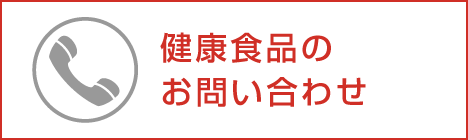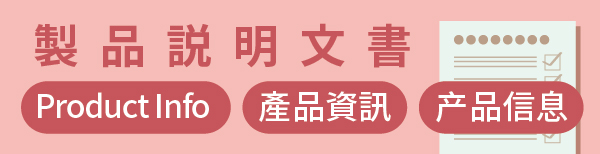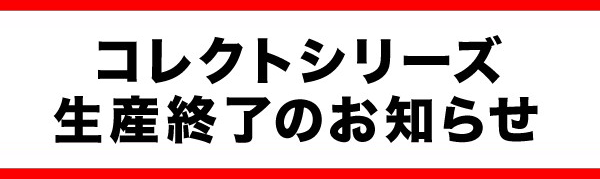かぜ・発熱
かぜとは?
かぜは咽頭、気管支などの、主に上気道における急性の炎症のことです。その8~9割はウィルス感染が原因といわれ、感染源となるウィルスは、鼻にとりつく「ライノウィルス」、のどに炎症をおこす「アデノウィルス」、高熱や関節症上など全身症状の強い「インフルエンザウィルス」をはじめ200種類以上にもおよぶといわれています。
発熱、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、咳、痰、食欲不振などの症状は、体内に入ってきた異物であるウィルスを追い出そうと抵抗するごく自然なからだの反応です。
そこで、市販のかぜ薬はウィルス感染そのものを治すというよりも、まず症状をやわらげるという対症療法の位置づけにあります。

かぜの予防
人の免疫力は、疲労やストレスをためこんだり、睡眠不足、栄養バランスの悪い食事などが原因で弱まります。すると、ウィルスに感染しやすくなり、かぜをひきやすくなるため、かぜを予防するには、ウィルスに負けない健康な体を維持することが何よりの対策です。そのためには、睡眠不足や過労などを避けて、十分な体力と免疫力をつけるよう、日頃からの健康管理が大切です。
とはいっても、いつも万全な体調でいるのはなかなか大変です。かぜのウィルスは、咳などによる飛沫感染と、手から手などへの接触感染が主な感染ルートです。できるだけウィルスに接触しないことも重要な予防策のひとつですから、外から帰ってきたら、まずは流水で手を洗い、うがいをする習慣をつけましょう。これだけの習慣でもかなり予防できます。また、外出時にはマスクをつけるのも効果的です。
とはいっても、いつも万全な体調でいるのはなかなか大変です。かぜのウィルスは、咳などによる飛沫感染と、手から手などへの接触感染が主な感染ルートです。できるだけウィルスに接触しないことも重要な予防策のひとつですから、外から帰ってきたら、まずは流水で手を洗い、うがいをする習慣をつけましょう。これだけの習慣でもかなり予防できます。また、外出時にはマスクをつけるのも効果的です。
かぜをひいたときは
かぜは「ひいたかな?」と自覚したらすぐに対処し、ウィルスの増殖を抑える早めの手当がもっとも大切です。
1. 安静にして、十分な休養と栄養、睡眠をとる
2. 室内を暖かくし、湿度を保つ
3. 室内のホコリ・チリやタバコの煙を排除
4. 汗をかいたらよく拭きとり、体を冷やさない

食事は栄養価の高い高タンパク食を
十分な栄養をとるには、消化の良い高タンパクな食品がいいでしょう。また、かぜのときには、皮膚や粘膜の健康を守り細胞の働きを助けるビタミンB群と、抗酸化力のあるビタミンCが多く消耗されるため、しっかり補給する必要があります。体の代謝を円滑にする効果もあるため、ビタミンは積極的に摂取しましょう。
かぜをひいたらこんな食事を
水分の補給を(野菜スープ、牛乳、ヨーグルトなど)
カロリー高く、消化しやすい食事(卵、やわらない肉など)
ビタミンをたっぷり接種(野菜、果物など)
油の多い料理は消化しにくいので避ける
カレーなど香辛料が多い刺激的な料理も避ける
薬は症状に合ったものを選んで
かぜ薬として処方される薬は、主に現れている症状をやわらげる「対症療法」のための薬です。市販薬には「総合感冒薬」といって、複数の諸症状に効き目のある成分を配合した薬と、「のどの痛み」「咳」「鼻水」など個々の症状に対応した薬があります。
「ひいたかな?」と思ったときには、早めに市販薬を服用するのも有効なかぜ対策といえるでしょう。
また、インフルエンザウィルスによる流行性感冒の場合は近年、抗ウィルス作用を持つ薬が開発され、その効果が知られるようになってきました。まず高熱が出るのがインフルエンザの特徴です。流行シーズンにインフルエンザが疑われる場合は、病院でウィルスの有無を検査してもらい、重症にならないうちに治療しましょう。
「ひいたかな?」と思ったときには、早めに市販薬を服用するのも有効なかぜ対策といえるでしょう。
また、インフルエンザウィルスによる流行性感冒の場合は近年、抗ウィルス作用を持つ薬が開発され、その効果が知られるようになってきました。まず高熱が出るのがインフルエンザの特徴です。流行シーズンにインフルエンザが疑われる場合は、病院でウィルスの有無を検査してもらい、重症にならないうちに治療しましょう。
かぜ薬の主な種類
- 解熱・鎮痛・抗炎症薬:頭痛、発熱、筋肉の痛みをやわらげる。
- 抗ヒスタミン薬:くしゃみ、鼻水、鼻づまりを抑えたりする。
- 総合感冒薬:解熱鎮痛薬、抗ヒスタミン薬、カフェインなどで総合的にかぜ症状を抑える。
- 咳を鎮める。
- 去痰薬:痰を出しやすくし、咳を軽くする。
- うがい薬:のどの痛み、いがらっぽさの緩和。口腔内の殺菌消毒。
- トローチ:のどの粘膜を保護する。