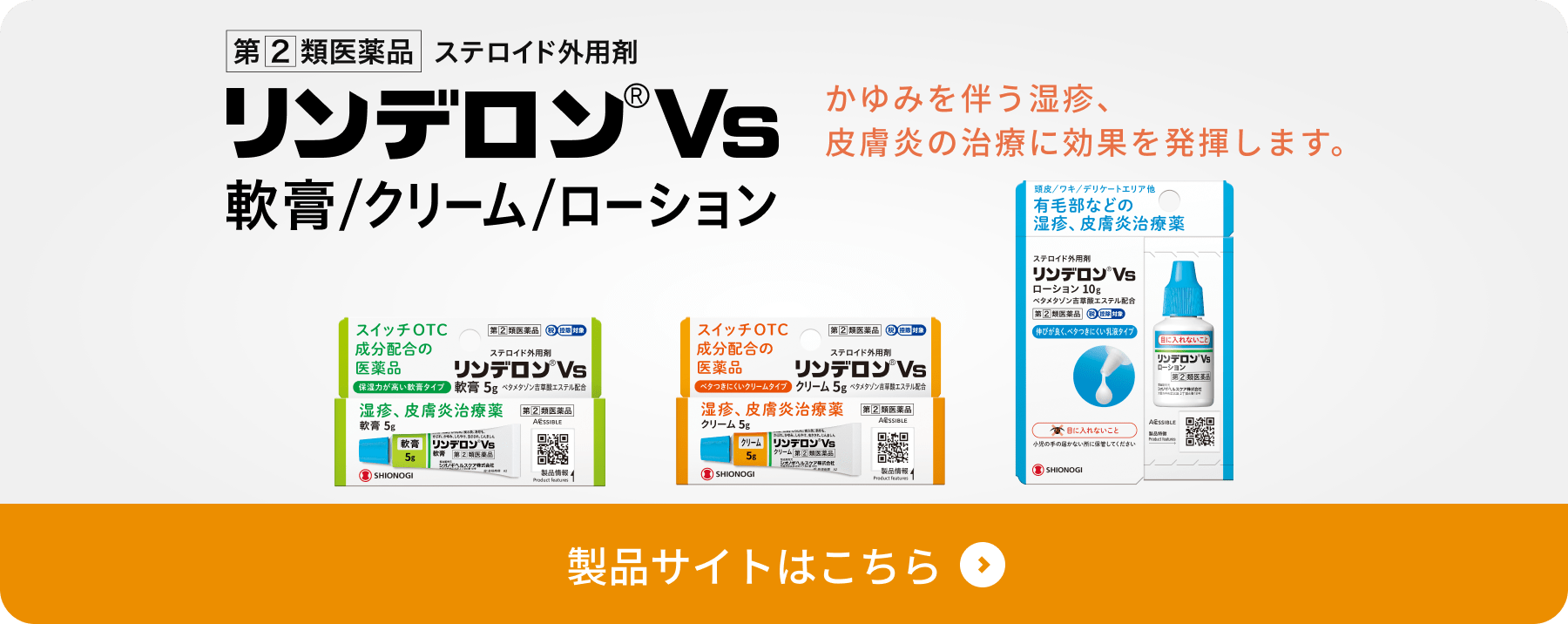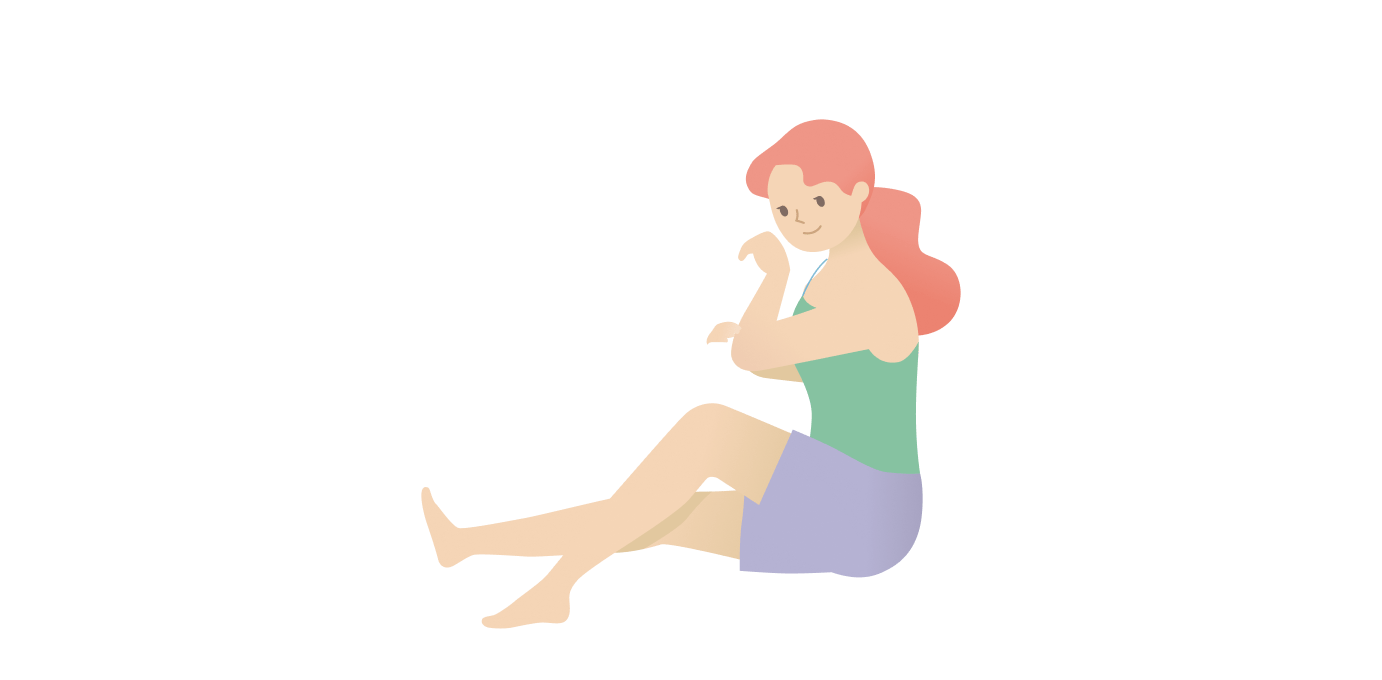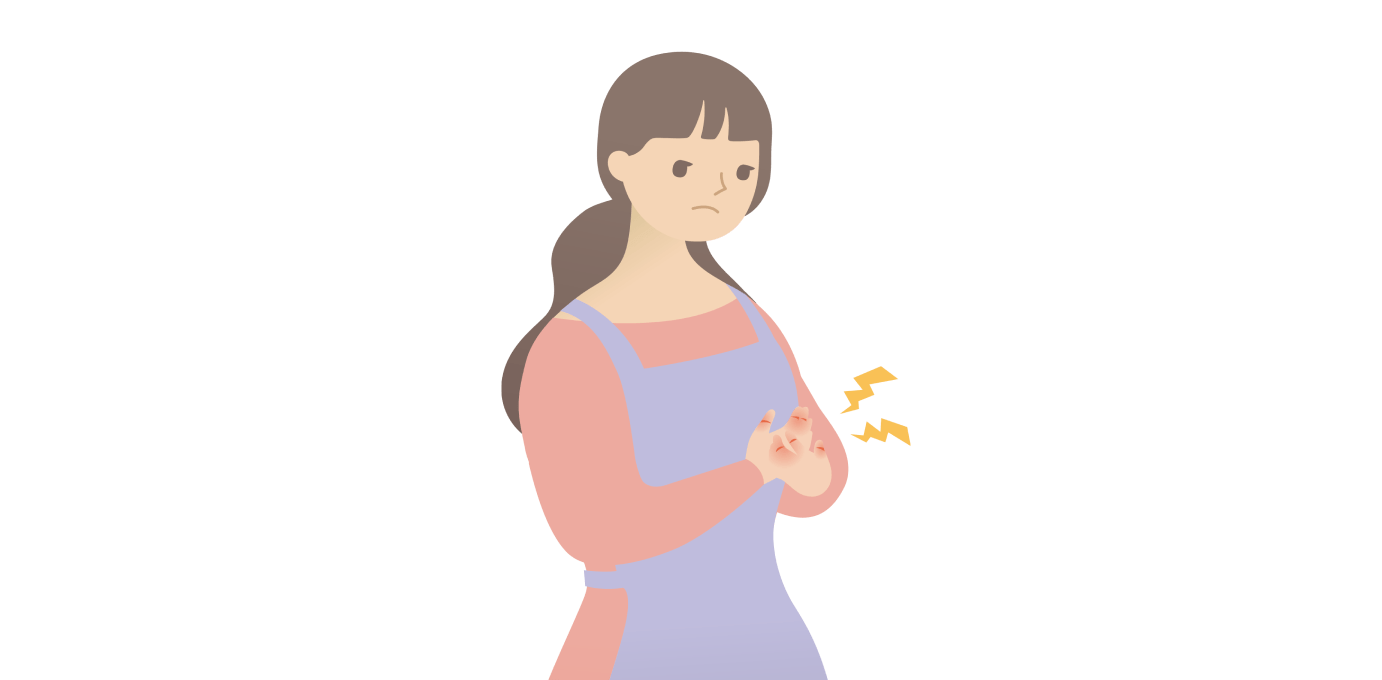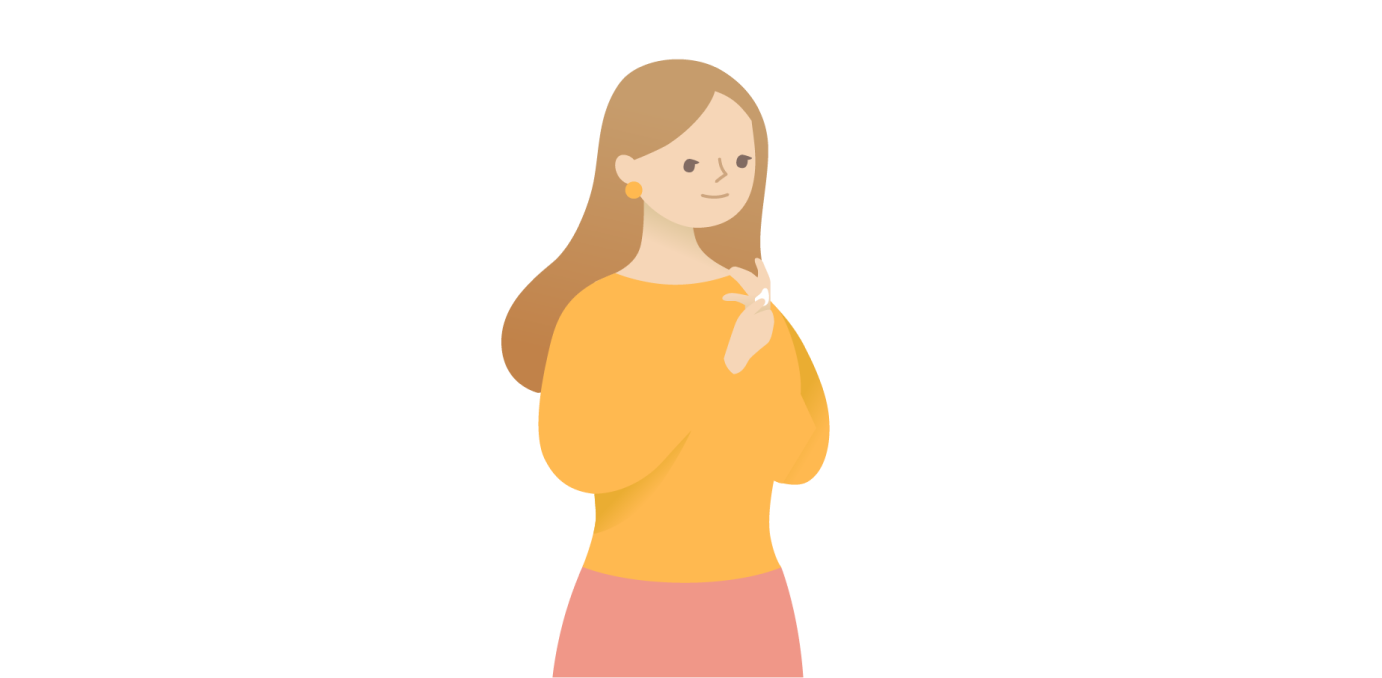しもやけ(凍瘡)の
原因&対処法

最終更新:
寒くなってくると手足などにできる「しもやけ(凍瘡)」。
今回はしもやけ(凍瘡)について、その原因や対処法をご紹介します。
しもやけ(凍瘡)とは?
しもやけ(凍瘡)とは、冬などの急に気温が下がった際に、かゆみをともなう赤色や赤紫色の腫れが現れる症状のことをいいます。おもに手足の指先、耳たぶといった身体の末端部にみられ、寒さが緩む春には症状が軽くなるのが特徴です。
子どもに多くみられ、ひどいときには水ぶくれや、皮膚が崩れてえぐれる「潰瘍」を生じることもあります。

- ※ 凍傷との違い
- 冬山登山などでおこる「凍傷」は、氷点下の寒さにさらされることで手足の指先、耳たぶといった身体の末端部の皮膚組織が急速に凍り、場合によっては壊死(細胞が死ぬこと)やミイラ化に至る症状のことをいいます。気温-12℃以下でおこることが多く、環境次第ではわずか数秒で凍傷が発生することもあります。
しもやけ(凍瘡)の原因
私たちの身体は、寒い環境下では、体内の熱を外に逃がさないように血管を収縮して体温を保っています。その際、動脈も静脈も収縮しますが、動脈の収縮は静脈よりも持続しません。体温を調節するために血管の収縮や拡張を繰り返すなか、動脈収縮が解除されたのに静脈は収縮が解除されず、血液の循環に障害がおこった結果、しもやけ(凍瘡)の症状が現れると考えられます。
厳しい寒さが続く時期よりも、初冬や初春などの寒暖差が激しい時期におこりやすく、ほかにも、発汗や遺伝的な要因が大きく関わる場合があるため、発症する明確なメカニズムはわかっていません。
しもやけ(凍瘡)の予防・対処法
- 寒さを避け保温する
- しもやけ(凍瘡)の原因となる寒さを避けるため、寒い冬には手袋や厚手の靴下、マスクや帽子、耳あてなどの防寒具を活用しましょう。使い捨てカイロなどの保温用品を携帯しておくのもよいでしょう。
- ビタミンEをとる
-
ビタミンEには血液の循環をよくする働きがあります。しもやけ(凍瘡)を毎冬おこす人は、早ければ10月上旬頃よりビタミンE製剤などを予防的に内服しておくとよいでしょう。また、アーモンド、落花生、うなぎ、ツナ缶といった、ビタミンEが多く含まれる食材を意識してとるようにしましょう。

- 市販薬で症状をおさえる
-
かゆみや腫れなどの症状には、抗炎症作用のあるステロイド外用剤(塗り薬)が有効です。自分の症状に適したステロイド外用剤(塗り薬)がわからない場合は、薬局・薬店の薬剤師、または登録販売者に症状を伝え、相談してみましょう。
春になっても症状が軽くならない場合や症状が強い場合、薬局・薬店で購入したステロイド外用剤(塗り薬)を5~6日使用しても改善がみられない場合は自己判断で使用を続けず、医療機関(皮膚科)を受診しましょう。若い女性にみられることの多い「エリテマトーデス」のような原因不明の自己免疫疾患でも、しもやけ(凍瘡)に似た症状が出る場合があります。